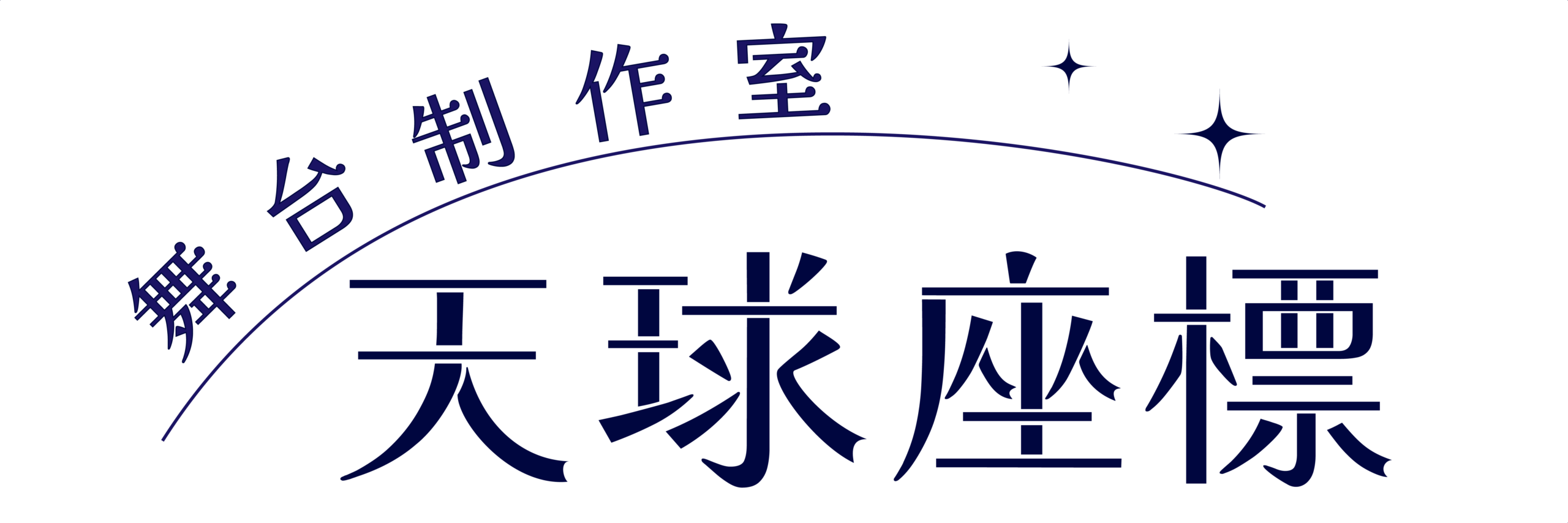舞台制作室 天球座標について
コンセプト
俳優・スタッフの多様な組み合わせで、化学反応を起こし、様々な在り方を検討する場の創出。
名前の由来
地球上から見上げると星空は平面に見えますが、実際の距離や大きさにはとても大きな差があります。
そんな星々を地球から観察する際の考え方の一つに、天球と言う言葉があります。
天球とは、公益社団法人日本天文学会が運営している天文学辞典において、以下のように書かれています。
観測者(自分)を中心として天体がそこに貼り付いているかのように見える仮想的な球面のこと。
天体の位置を表す観点から天球面と言うことも多い。
月、惑星、太陽、恒星、銀河などの天体までの距離は非常に遠いため、夜空を見上げてもそれらの距離を実感することはできない。
それらの天体は自分を中心とする丸天井に貼り付いているかのように見える。
この丸天井(球面)が天球である。天球は実在するものではない。
人類の歴史には天文学が常に身近にあり、人間は空を見上げ続けてきました。
晴天の日の夜に空を見上げれば、星空が目に飛び込んできます。
それらは時間や季節によって絶えず変化しています。
人は原始からそれらに意味を込め、目印にし、星座を作り、神話を編み、時には望みを託したり、時には目指して飛び立ったりしながら、想いを馳せてきました。
しかし、星自体は鉱石やガスの塊に過ぎません。
また自身で光り輝く星もあれば、照り返しで光っているように見えているだけの星もあります。
ですが、地球から見上げると、どれも綺麗な星々に見えます。
星自体の成分の構成や光り方、寿命、地球からの距離は、それぞれ大きく違います。
ですが、地球にいる観測者から見れば、星々はどれも綺麗に見えます。
その在り方は、舞台演劇の在り方に非常に近いように感じておりましたので、その想いを込めて名前を決めました。
設立理念・運営目的
1.役者やスタッフの多様な組み合わせの実現。
劇団やユニットの枠に囚われない多様な組み合わせの実現を目指しています。
2 .“場数”の確保。
俳優の舞台出演機会を増やすこと、観客の“観る機会”を増やすことを目指しています。
3 .若手演劇人の視野拡大の促進。
収支や広報、制作上の具体的な課題等を共有し、「舞台を作る人材」の発掘・育成を狙います。
4 .地方小劇場演劇における“持続可能性”への挑戦。
どれくらいの予算で、どのように運用すれば、どのような公演が可能か、というようなシステムを検討し続け、地方小劇場演劇の持続可能性を追求していきます。
5 .コンパクトで計画的な舞台制作。
1~4を達成するためのコンパクトなシステムを検討、構築していくことを目指しています。